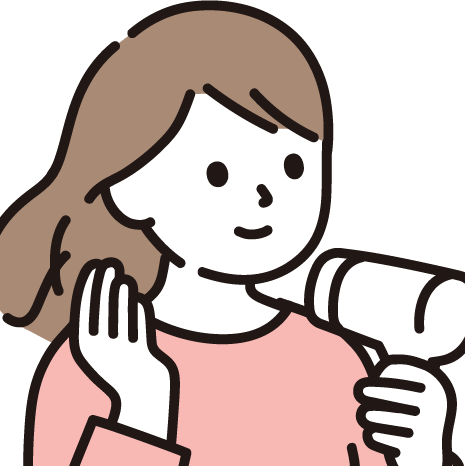
カメラ買いたいんだけど、初心者すぎて何にもわからない!色々自分で調べてみるんだけど専門用語とか出てきて余計にわからなくなる・・・。とりあえず一眼レフとミラーレスの違いから教えて・・・!
これからカメラを買いたい人に向けて、それぞれの専門用語や役割の解説、選び方のコツをまとめました。カメラデビューを検討している人はぜひ参考にしてみてください!
- カメラ/メーカーの選び方
- 一眼レフとミラーレスの違い
- センサーサイズの違い
- レンズの選び方
- カメラを使ってできること
一眼レフとミラーレスの違い

カメラのことを調べていると、出てくるキーワードに「一眼レフ ミラーレス」があります。それぞれの違いが分かれば今後のレンズ選びや予算も組みやすくなるため、正しく理解してカメラ選びをスタートさせましょう。
一眼レフとミラーレスの違いは次の通りです。
| 項目 | 一眼レフ | ミラーレス |
|---|---|---|
| 主な発売時期 | 〜2020年まで | 2018年から〜 |
| 重さ | △ | ◎ |
| 撮影のしやすさ | △ | ◎ |
| バッテリー持ち | ○ | △ |
| レンズの種類 | ◎ | ○ |
| 将来性 | × | ◎ |
特に、撮影のしやすさと将来性の面で比較した場合、ミラーレスの方がかなり有利です。
それぞれの項目を具体的に解説していきます。
一眼レフとミラーレスの主な発売時期
一眼レフカメラで大きなシェアを獲得していた「ニコン」や「キヤノン」といったメーカーは、2020年あたりで新機種の製造発売を終了しています。※ペンタックスを除く。
2018年あたりからはミラーレスカメラの需要が高まり、一眼レフと代わって完全な世代交代が行われました。
現在は、ソニー・富士フィルム・OM-SYSTEM(オリンパス)・パナソニックなどを含め、各社から発売される全てのカメラは「ミラーレス一眼カメラ」となっています。※ペンタックスを除く。
ミラーレスカメラは将来性がある?
先ほども触れたように、一眼レフカメラの新機種を製造しているメーカーはペンタックスのみです。
ニコンやキヤノン、ソニーといった大手メーカーは、将来的にも一眼レフカメラの新機種を作らないばかりか、部品がなくなるとメーカーによる修理対応も行われなくなります。
そのため、新製品の開発や修理の面でも、ミラーレスカメラの方が将来性のあるカメラと言えます。
一眼レフはレンズの種類が多い?
カメラの醍醐味はレンズ交換ができることです。一眼レフとミラーレスでレンズ本数を比較すると、一眼レフの方が歴史が長いこともあり、使えるレンズが豊富にあります。
反対に、ミラーレスカメラの場合はまだ歴史が浅く、一眼レフカメラに比べるとレンズの数が少ないです。とはいえ、毎年新しいレンズが発売されており、プロでも十分に撮影できる本数がラインナップされています。
また、「マウントアダプター」を使用すれば、ミラーレスカメラに一眼レフや他社メーカーのレンズを装着できるため、レンズが少ない問題は簡単に解決します。
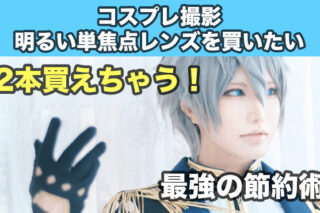
ミラーレスの方が撮影しやすい?
ミラーレスカメラは一眼レフカメラと違い、直感的に撮影ができる点が魅力です。
基本的な一眼レフカメラの場合、撮影して画像を確認するまでは写真の色味がわかりません。
ミラーレスカメラの場合、ファインダーや液晶画面を覗いている段階で色味の設定がリアルタイムに反映されます。
そのため、一眼レフのような取り直し回数が激減し、シャッターチャンスだけに集中できます。普段からスマホで写真を撮影することが多い人は、ミラーレスカメラの方が比較的スムーズにカメラデビューできるはずです。
ミラーレスはバッテリーの減りが早い?
ミラーレスカメラは一眼レフカメラに比べて電池の減りが早いです。撮影枚数などにもよりますが、ミラーレスカメラを使いたい人はバッテリーの予備をセットで購入しておくのがおすすめです。
イメージとしては、一眼レフカメラの電池持ちはミラーレスカメラの約1.5倍〜です。
ちなみに、多くのミラーレスカメラは本体に直接ケーブルを挿して充電できるものが多いです。一眼レフカメラだとバッテリーを本体から取り外して充電する必要があるため、その点はミラーレスカメラの方が便利と言えます。
ミラーレスは軽い!
同じクラスのカメラと比べても、一眼レフカメラよりミラーレスカメラの方が圧倒的に軽いです。サイズも小さいものが多いため、気軽に持ち出せるのも魅力。
当然軽い方が撮影中も疲れにくく、手ブレしないメリットもあります。また、カメラ自体が軽いと三脚などもコンパクトなものを選べます。
軽くて小さければカメラバッグの選択肢も広がるため、トータルでフットワークの軽い撮影を楽しめます。
センサーサイズとは?

カメラ中央にある長方形の部分がセンサーです。
「センサーサイズ」も、カメラに関する情報を調べるとよく出てくるキーワードです。センサーサイズを簡単に説明すると、レンズから入った光をデジタル情報に変換してくれる「センサーの大きさ」を指します。
センサーサイズ(撮像素子)のことを理解すると、カメラとレンズの選択肢を一気に絞れます。予算はもちろん、写真のクオリティにも大きく関わってくるため、カメラにとってセンサーサイズは重要な要素です。
主なセンサーサイズの種類と違いは以下の通りです。
| 項目 | フルサイズ | APS-C | マイクロフォーサーズ |
|---|---|---|---|
| ボケ | すごく柔らかい | ほどよく柔らかい | あまりボケない |
| 画角 | 広い | 少し狭い | 狭い |
| 画質 | 高画質 | 高画質 | 良好 |
| ノイズ | 少ない | 少なめ | 少し目立つ |
| サイズ/重量 | 大きく重い | コンパクト | 最もコンパクト |
画質面だけでいうと「フルサイズ」センサーが圧倒的に有利です。画質以外でもセンサーごとに細かな特徴があので、それぞれ具体的に解説します。
フルサイズセンサーはよくボケる

写真のクオリティを大きく左右する”ボケ”ですが、センサーサイズが大きいほどボケ量が多いです。そのため、フルサイズセンサーは最もボケに有利です。
次いでAPSーC、マイクロフォーサーズに続きます。とにかくボケがキレイな写真を撮りたい人は、フルサイズセンサーを搭載したカメラを購入するのがおすすめです。
センサーによって画角が変わる
レンズはもちろんですが、カメラに搭載されているセンサーサイズによっても撮影できる画角が変わります。
例えば、24〜200mmのレンズを使用する場合、センサーサイズによって次のような画角(焦点距離)となります。
| フルサイズ(x1) | APS-C(x1.5) | マイクロフォーサーズ(x2) |
|---|---|---|
| 24mm | 36mm | 48mm |
| 50mm | 75mm | 100mm |
| 85mm | 127.5mm | 170mm |
| 200mm | 300mm | 400mm |
表のように、センサーが大きい方が広く撮影でき、小さい方が狭く撮影できます。※フルサイズセンサーを”1倍”の画角として扱い、APS-Cは1.5倍、マイクロフォーサーズは2倍扱いとなります。
そのため、広角が必要となる風景写真にはフルサイズカメラが人気で、野鳥撮影など望遠を必要とする写真にはマイクロフォーサーズカメラが人気を集めています。
センサーが大きければ高画質?
センサーのサイズが大きいと、写真に重要な要素である”光”をたくさん取り込めます。光が多いと「諧調表現」が豊かになり、クオリティの高い写真を撮影できます。
特に、カメラにとって苦手といわれる明暗差の激しいシーンでは、センサーサイズによる画質の差が大きく出ます。
そのため、センサーの大きいフルサイズカメラは白飛びや黒つぶれが比較的抑えられるので、画像の加工(レタッチ)の幅が広がる点も強みとなります。
センサーが大きければノイズが少ない?
夜などの暗い場所で撮影した際、ISO感度(明るさのコントロール)の設定によって画像にノイズが乗ります。ノイズの量はカメラの性能によって異なりますが、搭載しているセンサーによっても大きく変わります。
一般的にセンサーサイズの大きい方がノイズが少なく、小さい方がより多くのノイズが残ります。
特に、暗い場面の撮影ではノイズが目立ちやすくなるため、美しくシャープに写真を残したい場合、フルサイズセンサーのカメラを使った方が比較的キレイに撮影できます。
カメラの重さやサイズに比例する?
大きいセンサーを搭載するということは、それだけカメラのサイズや重量も増加する傾向にあります。とにかく軽量コンパクトなカメラが欲しい場合、センサーが小さいマイクロフォーサーズなどのカメラがおすすめです。
フルサイズセンサーを搭載したカメラよりも画質面では劣りますが、比較的フットワークの軽い撮影が楽しめます。とはいえ、フルサイズセンサー搭載のカメラでも小型軽量のモデルが発売されているため、カメラ選びの際にはセンサーサイズとカメラの重量も合わせて比較してみましょう。
メーカーの選び方

結論から言うと、どこのメーカーでもキレイな写真は撮れます。公式サイトやYoutubeなどを閲覧し、興味を惹かれるカメラがあれば直感で選んでみるのもおすすめです。
主なメーカーの特徴は次の通りです。
| 項目 | ニコン | キヤノン | ソニー | 富士フィルム | OM-SYSTEM | パナソニック | ペンタックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサーサイズ | APS-C/フルサイズ | APS-C/フルサイズ | APS-C/フルサイズ | APS-C | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ/フルサイズ | APS-C |
| レンズ本数 (ミラーレス) |
約41本 | 約44本 | 約69本 | 約43本 | 約37本 | 約53本 | 約39本 (一眼レフ) |
| 操作性 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 防塵防滴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| 手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ |
| 色味・作風 | 忠実に表現 | 記憶色 | 透明感 | クラシカル | 鮮やかな青 | ナチュラル | 鮮やかな緑 |
| 人気機種 | Nikon Z f | EOS R8 | α7III | X-T5 | OM-1 MarkII | LUMIX DC-G9 | K-1 MarkII |
メーカーごとに写真の色味や操作性、オプション機能が異なるため、それぞれ具体的に解説します。
ニコン

色味は忠実に再現する傾向があり、見えたままの色にこだわりたいカメラマンに人気があります。手ブレ補正や防塵防滴も良好で、どんな場面でもしっかり活躍してくれます。操作性も良く、一眼レフ・ミラーレス問わず同じような操作感覚で撮影できる点も、ニコンの魅力となっています。
2024年時点でのニコン純正レンズ本数(ミラーレス)は約41本で、マウントアダプターを使用すれば、一眼レフ時代のレンズや他社メーカーのレンズも装着可能です。
ニコン人気機種「Nikon Z6II」
ファインダー・モニターともに高解像度で、クリアな視界で撮影できるのが魅力。暗所でのAF性能も高く、”人や動物”といった被写体を自動判別する機能が搭載されています。特に人物撮影では、「人物印象調整」を活用できるのが特徴。色相(マゼンタ・イエロー)と明るさを自由に調整し、シーンごとに理想的なイメージで撮影できます。
メモリーカードはダブルスロットで、高速タイプの”XQDカード/CFexpressカード”に対応しています。
| 基本仕様 | 詳細 |
|---|---|
| タイプ | ミラーレス |
| 画素数 | 2528万画素(総画素) 2450万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50相当、204800相当 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約5.5コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2インチ 210万ドット |
| ファインダー倍率 | 0.8倍 |
| ファインダー視野率 | 100% |
| 電池タイプ | 専用電池型番: EN-EL15c |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:340枚 液晶モニタ使用時:410枚 |
| 記録メディア | XQDカード CFexpressカードTypeB SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット XQDカード・CFexpressカードTypeB/SDカード |
| その他機能 | |
| 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit |
| タイム | ○ |
| セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、miniHDMI |
| AFセンサー測距点 | 273点 |
| 動画撮影 | |
| 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 59.94fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
| 音声記録方式 | リニアPCM AAC |
| ネットワーク | |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| サイズ・重量 | |
| 幅x高さx奥行き | 134x100.5x69.5mm |
| 重量 | 約705g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約615g(本体のみ) |
キヤノン

色味は記憶色で表現する傾向があり、健康的な肌色を表現できるポートレートなどを撮影したいカメラマンに定評があります。手ブレ補正や防塵防滴も良好で、どんな場面でもしっかり活躍してくれます。操作性も良く、比較的丸みを帯びたデザインで手によく馴染むのもキヤノンの魅力となっています。
2024年時点でのキヤノン純正レンズ本数(ミラーレス)は約44本で、マウントアダプターを使用すれば、一眼レフ時代のレンズや他社メーカーのレンズも装着可能です。
キヤノン人気機種「EOS R6 mark II」
安心の手ブレ補正はもちろん、独自のAFシステム「デュアルピクセルCMOS AF II」を搭載しているのが特徴で、”人物、犬、猫、鳥、馬、車、バイク、鉄道、飛行機”といった様々な被写体を判別し、自動でピントを合わせてくれます。液晶画面はバリアングル液晶で、構図決めも簡単に行えます。
前機種のR6からバッテリー性能や画素数も向上し、「OVFビューアシスト」の搭載で、ファインダーの見え方を自由に切り替えできるのも強みとなっています。
| 基本仕様 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ミラーレス | ||
| 画素数 | 2560万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
||
| 撮像素子 | フルサイズ 36mm×24mm CMOS |
||
| 撮影感度 | 標準:ISO100~102400 拡張:ISO50、204800 |
||
| 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF | ||
| 連写撮影 | 電子シャッター時:最高約40コマ/秒 電子先幕・メカシャッター時:最高約12コマ/秒 |
||
| シャッタースピード | 電子:1/16000秒、1/8000秒~30秒 電子先幕・メカニカル:1/8000秒~30秒 |
||
| 液晶モニター | 3インチ 162万ドット |
||
| ファインダー形式 | 有機ELカラー電子ビューファインダー | ||
| ファインダー倍率 | 0.76倍 | ||
| ファインダー視野率 | 100% | ||
| 電池タイプ | 専用電池型番: LP-E6NH | ||
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:320枚 液晶モニタ使用時:580枚 |
||
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
||
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
||
| その他機能 | |||
| 防塵防滴 | ○ | ||
| 手ブレ補正機構 | ○ | ||
| 5軸手ブレ補正 | ○ | ||
| 自分撮り機能 | ○ | ||
| タッチパネル | ○ | ||
| ゴミ取り機構 | ○ | ||
| 内蔵フラッシュ | × | ||
| タイムラプス | ○ | ||
| ライブビュー | ○ | ||
| 可動式モニタ | ○ | ||
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | ||
| RAW(14bit) | ○ | ||
| PictBridge対応 | × | ||
| セルフタイマー | ○ | ||
| USB充電 | × | ||
| バルブ | ○ | ||
| インターフェース | HDMIマイクロ、USB Type-C | ||
| 起動時間 | 0.4秒 | ||
| AFセンサー測距点 | 最大4,897 | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | ○ | ||
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 59.94fps | ||
| ファイル形式 | MP4 | ||
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵、外部マイク:マルチアクセサリーシュー、3.5mmステレオミニジャック | ||
| 音声記録方式 | IPB:AAC/リニアPCM(音声圧縮:する/しない) IPB(軽量):AAC |
||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | ||
| Bluetooth | ○ | ||
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | ||
| Wi-Fi Direct対応 | × | ||
| NFC | × | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 138.4x98.4x88.4mm | ||
| 重量 | 約670g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約588g(本体のみ) |
||
ソニー

色味は透明感があり、色彩やかな写真を撮影したいカメラマンに人気があります。手ブレ補正や防塵防滴も良好で、どんな場面でもしっかり活躍してくれます。操作性も良く、瞳に自動でフォーカスを合わせてくれる高性能な「瞳AF」もキヤノンの魅力となっています。
2024年時点でのソニー純正レンズ本数(ミラーレス)は約69本で、マウントアダプターを使用すれば、一眼レフ時代のレンズや他社メーカーのレンズも装着可能です。
FUJIFILM

色味はクラシカルで、フィルムで撮影したような写真表現がしたいカメラマンに定評があります。手ブレ補正や防塵防滴も良好で、どんな場面でもしっかり活躍してくれます。操作性はダイヤルボタンがあるため少し慣れが必要ですが、他のメーカーにはないデザイン性が楽しめる設計となっています。
カメラに搭載されている「フィルムシミュレーション」もFUJIFILMの醍醐味で、昔ながらのフィルム撮影を気軽に表現できます。
2024年時点でのFUJIFILM純正レンズ本数(ミラーレス)は約43本で、マウントアダプターを使用すれば、他社メーカーのレンズも装着可能です。
OM-SYSTEM(オリンパス)

色味は高発色なブルーが特徴で、センサーサイズの小ささを活かした望遠撮影を楽しみたいカメラマンに定評があります。手ブレ補正や防塵防滴は群を抜いており、機種やレンズによっては大雨に濡れるような撮影にも耐えられます。
操作性は慣れるまで多少の時間がかかりますが、ボタン割り当ての柔軟なカスタマイズ性もあり、軽量コンパクトな点もOM-SYSTEMの魅力となっています。
2024年時点でのOM-SYSTEM純正レンズ本数(ミラーレス)は約37本で、マウントアダプターを使用すれば、他社メーカーのレンズも装着可能です。
パナソニック

色味はナチュラルな発色が特徴で、本格的な動画撮影も楽しみたいカメラマンに定評があります。手ブレ補正や防塵防滴も良好で、どんな場面でもしっかり活躍してくれます。操作性も良く、世界的に有名なドイツの「ライカ」との協業レンズを使用できるのも魅力です。
2024年時点での純正レンズ本数(ミラーレス)は約53本で、マウントアダプターを使用すれば、他社メーカーのレンズも装着可能です。
ペンタックス

色味はグリーンの鮮やかな発色が特徴で、高い防塵防滴性能から、過酷でタフな撮影を楽しみたいカメラマンに定評があります。手ブレ補正は他社に比べると比較的弱めですが、撮影に支障はありません。操作性は少し慣れが必要ですが、頑丈なボディで安心して撮影できる点は他社にない大きな魅力です。
2024年時点での純正レンズ本数は約39本で、マウントアダプターを使用すれば、他社メーカーのレンズも装着可能です。
カメラの選び方

”メーカーの選び方”で触れた内容も参考に、数あるカメラの中から選択肢を絞り込んでいきましょう。
次の要点をおさえれば選びやすくなるはずです。
- 一眼レフかミラーレスか 「カメラ市場のメインはミラーレスカメラ」
- 価格 「予算オーバーだとそもそも購入できない」
- 発売日 「発売日がすごく古いカメラは避ける」
- センサーサイズ 「画質と画角に影響する」
- 液晶画面 「可動式がおすすめ」
- ファインダー 「撮りやすさに直結する」
- 重さ 「長時間撮影を想定してみる」
- デザイン 「撮影モチベーションの維持」
それぞれ具体的に解説します。
一眼レフかミラーレスか
「カメラ市場のメインはミラーレスカメラ」
現在、デジタル一眼レフカメラはペンタックス以外製造しておらず、ミラーレスカメラが市場のシェアを占めています。
”一眼レフとミラーレスの違い”でも説明した通り、ミラーレスカメラは色味の設定が液晶やファインダーへリアルタイムに反映されるため、初心者でも撮影しやすいカメラになっています。
さらに修理対応まで考えるなら、ペンタックスを除く一眼レフは発売日が古く、メーカーでも修理できないカメラが多くなっています。そのため、将来的にはミラーレスカメラの方が修理面で考えても長く使えるメリットがあります。
予算を決める
「予算オーバーだとそもそも購入できない」
カメラに関わらず、レンズも含めた大前提のお話ですが、最初に予算を決めましょう。
予算内で大まかに調べていくと、購入できそうな価格帯のカメラが絞り込めます。そのうえで新品で購入するか、中古で状態の良いものを探すか検討していきましょう。
発売日をチェックする
「発売日がすごく古いカメラは避ける」
古い機種は画質面で大きく差があったり、ファインダーや液晶画面が見づらいカメラがあります。
あくまで性能的な目安ですが、一眼レフなら2015年以降発売、ミラーレスなら2018年以降に発売された機種から探してみましょう。
センサーサイズにこだわる
「総合的な画質に直結する」
”センサーサイズとは?”で解説したように、ボケやノイズ、諧調表現といった面で大きく影響します。とにかくボケを優先したい場合はフルサイズカメラを選択しましょう。
FUJIFILMなど、APS-Cセンサーしか発売していないカメラでも、フィルムシミュレーション機能をはじめとした他社にない魅力を備えたカメラがあります。
画質面だけでなく、各メーカーの魅力も加味しながらセンサーサイズを選んでみましょう。
液晶画面の仕組みをチェックする

「可動式がおすすめ」
現在はミラーレスカメラを中心に、液晶画面が可動するタイプが主流となっています。液晶画面は機種によって可動する範囲が異なるため、(チルト/バリアングルなど)購入前に公式サイトやYoutubeで確認しておきましょう。
撮影において液晶画面が動くことのメリットは次の通り。
- 自由なアングルで撮影できる
- 狭い場所でも撮影しやすくなる
- 動画撮影がしやすくなる
それぞれを簡単に解説します。
液晶画面が動くことで、カメラを上に向けた俯瞰撮影や、下からのあおり撮影などが簡単に行えます。
もし液晶画面が固定されている場合、画面を確認しながらの撮影が困難なため、取り直しの回数がかなり多くなってしまいます。
気軽にバリエーション豊富な撮影ができるので、新しい構図にも積極的にチャレンジできます。
「狭くてこれ以上後ろに下がりきれない」といった場面では、可動式の液晶があると便利に撮影できます。
ファインダーを除く必要がない分、カメラを頭ひとつ分後ろに引いて撮影できるため、少し広角に撮影しやすくなります。
意外と使う場面は多いため、可動式液晶のメリットを効果的に活かせます。
動きながらの撮影が多い動画撮影では、撮影者の視野確保も大切な要素です。
液晶画面がある程度自由に動くことで、様々な構図で撮りやすいことはもちろん、雰囲気や環境の変化に対応しやすくなります。
写真撮影にくわえ、動画撮影を考えている場合は特に可動式液晶の恩恵を受けられます。
ファインダーの有無をチェックする
「撮りやすさに直結する」
ファインダーの有無や位置は、写真の撮りやすさに影響を与えます。個々の撮影スタイルにもよりますが、ファインダーがあると構図やピントにより集中できたり、太陽光などの反射に強いというメリットがあります。
通常、ファインダーはカメラの中央上部に備わっていますが、機種によっては左端に位置する場合もあります。
また、一眼レフのように、全てのカメラにファインダーが備わっているわけではありません。ミラーレスカメラでは液晶画面のみ搭載されているものがあるため、液晶画面の稼働有無と合わせて検討してみましょう。
重さをチェックする
「長時間撮影を想定してみる」
写真を楽しむ場合、ある程度の長時間撮影が想定されます。
個人差はありますが、カメラがあまりに重たいと集中して撮影するのが困難です。また、手ブレしやすくなると失敗写真を量産してしまうかもしれません。
さらに、カメラを選ぶ際はレンズの重さもプラスされます。機材が増えていくほどカメラバックも重くなるため、「このサイズ・重さのカメラでどのくらい撮影に持ち出せそうか?」という観点で選んでみましょう。
デザインにも注目する
「撮影モチベーションの維持」
デザインもカメラ選びの大切な要素です。機能性や価格だけで選んでも、カメラのデザインが気に入らなければ撮影モチベーションが低下してしまうかもしれません。
全体的にはカメラのデザインに大きな差はありませんが、じっくり見比べてみるとメーカーごとに特徴があります。例えば「ニコン」のカメラは、ボディに赤色のアクセントカラーが取り入れられており、「フジフィルム」のカメラはクラシックな外観になっています。
性能面ももちろん重要ですが、思わずカメラを持ち出したくなるような”デザイン”にもこだわって選んでみましょう。
レンズの選び方

まずは、自分が撮影したいジャンルをおおまかにイメージしてみましょう。 よく連想されるものだと、「人物・風景・花・動物・スポーツ」などが挙げられます。 ジャンルを思い浮かべると、選択肢が次のように絞りこめます。
| ジャンル | 焦点距離 | 絞り |
|---|---|---|
| 人物 | 50〜105mm | f1.8〜f2.8 |
| 風景 | 12〜24mm | f2.8〜 |
| 動物 | 70〜300mm | f2.8〜 |
| スポーツ | 70〜400mm | f2.8〜f5.6 |
表にまとめたように、レンズには「焦点距離」「絞り」といった様々な数値が記されています。レンズ選びにはそれらの数値だけでなく、「マウント」の知識も必要です。
数値の意味や役割、マウントについて理解すると、具体的なレンズ選びができるようになります。覚えてしまえば簡単なので、順を追って理解していきましょう。
それぞれの項目を解説していきます。
焦点距離は撮影できる画角
レンズ名『NIKKOR Z 50mm f/1.8』に記されている「50mm」の部分で、画角を意味しています。この数値が小さいほど広角に、大きいほど望遠で撮影できます。
焦点距離が1つしか表記されていないレンズは「単焦点レンズ」と呼ばれ、同じ画角でのみ撮影が可能です。
また、『NIKKOR Z 24-120mm f/4』のように、ハイフンで焦点距離が2つ表記されているレンズは「ズームレンズ」と呼ばれ、単焦点レンズよりも幅を持たせた自由な画角で撮影できます。
それぞれの焦点距離による画角イメージは次の通りです。

12mm

50mm

100mm

200mm

400mm
写真は被写体と背景の距離が遠く、望遠で撮影するほど背景はよくボケます。また、次に解説する「絞り」の数値が低いほどさらにボケるため、絞りについても理解していきましょう。
絞りはピントの合う範囲

レンズ名『NIKKOR Z 50mm f/1.8』に記されている「f/1.8」の部分で、レンズの明るさを意味しています。
絞りの役割は2つあり、ボケ具合と明るさに影響します。数値が小さいほどよくボケて、明るい写真を撮影しやすくなります。
絞りの数値増減はカメラ側で操作できますが、レンズ名に記されている数値未満には設定できません。とにかくボケがキレイな写真を撮りたいときは、f値が小さいレンズを探してみましょう。
| 絞り数値表 | F1.0 | F1.1 | F1.2 | F1.4 | F1.6 | F1.8 | F2.0 | F2.2 | F2.5 | F2.8 | F3.2 | F3.6 | F4.0 | F4.5 | F5.0 | F5.6 | F6.3 | F7.1 | F8.0 | F9.0 | F10 | F11 | F13 | F14 | F16 | F18 | F20 | F22 | F25 | F29 | F32 |
|---|
マウントが合わないとレンズが装着できない
マウントとは、カメラとレンズに備わっている接合部分(規格)のことです。
カメラのセンサーサイズによってマウントの大きさや規格が異なるため、メーカーが一緒だからといって、必ず装着できるわけではありません。
レンズ選びをする際は、事前にマウントの仕組みを必ず理解しましょう。
以下、メーカーごとのマウント表です。
| レンズタイプ | 説明 |
|---|---|
| AF-S | 一眼レフ「フルサイズ・APS-C」 |
| AF-S DX | 一眼レフ「APS-C・フルサイズ※」 |
| 1 NIKKOR | ミラーレス一眼 Nikon1シリーズのレンズ「APS-C専用」 |
| Z | ミラーレス一眼 Zシリーズのレンズ「フルサイズ・APS-C」 |
| Z DX | ミラーレス一眼 Zシリーズのレンズ「APS-C・フルサイズ※」 |
※AF-S、Z DXレンズはフルサイズカメラにも装着できますが、クロップ(自動トリミング)され、画角が狭くなります。
| レンズタイプ | 説明 |
|---|---|
| EF | 一眼レフ「フルサイズ・APS-C」 |
| EF-S | 一眼レフ「APS-C専用」 |
| EF-M | ミラーレス一眼 EOS Mシリーズのレンズ「APS-C専用」 |
| RF | ミラーレス一眼 EOS Rシリーズのレンズ「フルサイズ・APS-C」 |
| RF-S | ミラーレス一眼 EOS Rシリーズのレンズ「APS-C・フルサイズ※」 |
※RF-Sレンズはフルサイズカメラにも装着できますが、クロップ(自動トリミング)され、画角が狭くなります。
| レンズタイプ | 説明 |
|---|---|
| FE | ミラーレス一眼「フルサイズ・APS-C」 |
| E | ミラーレス一眼「APS-C・フルサイズ※」 |
| 表記なし | 一眼レフ αシリーズのレンズ「フルサイズ専用」 |
| DT | 一眼レフ αシリーズのレンズ「APS-C専用」 |
※Eレンズはフルサイズカメラにも装着できますが、クロップ(自動トリミング)され、画角が狭くなります。
| レンズタイプ | 説明 |
|---|---|
| X | ミラーレス一眼「APS-C」 |
| GF | ミラーレス一眼「中判※」 |
※フルサイズカメラよりも大きい、中判カメラの専用レンズです。
| レンズタイプ | 説明 |
|---|---|
| D FA | デジタル一眼レフ「フルサイズ・APS-C」 |
| DA | デジタル一眼レフ「APS-C・フルサイズ※」 |
| FA | フィルム一眼レフ「フルサイズ専用」 |
※DAレンズはフルサイズカメラにも装着できますが、クロップ(トリミング)され、画角が狭くなります。
カメラを使ってできること
一眼レフやミラーレスカメラといったレンズ交換式のカメラがあれば、広角・望遠問わず高画質な写真を残せます。
細かい設定やボケ表現をマスターし、クオリティの高い写真撮影を目指しましょう。



また、カメラとレンズだけでなく、ストロボやLEDを使った撮影ができるのも醍醐味です。自分が意図する位置に光を配置し、被写体を活かすシルエット効果や影の演出も楽しめます。
環境やシチュエーションに合わせて光の強度や角度を調整し、個性的でクリエィティブな創作活動に挑戦するのもおすすめです。
まとめ
今回はカメラデビューを考えている人向けに、専門用語を解説しながら一眼レフとミラーレスの違いなどを中心に紹介しました。
カメラがあると写真撮影が楽しくなり、新しい趣味や出会いの場も広がります。今まで様々な専門用語でカメラに対する苦手意識があった人も、この記事を参考にしながら是非カメラデビューしてみましょう!

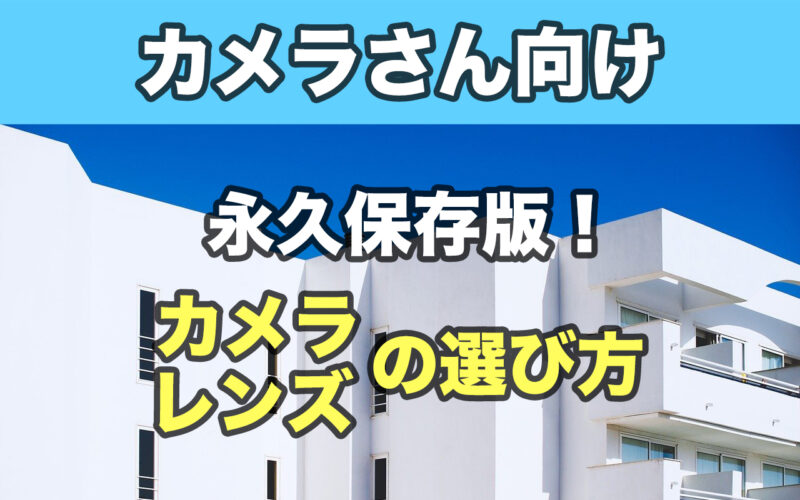


コメント